
 |
|
|
 |
|
|
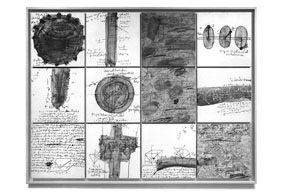 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
立体交差する分割
|
|
|
 |
|
抹茶碗の釉掛けでは胴を指で鷲づかみし、そのまま釉を掛ける。当然指でつかんだ部分に釉は掛からず指跡が残る。作る側も見る側もすでに常識で誰もそれを傷とは思わない。景色としてそれを観賞する風すらある。 |
 |
|
|
 |
|
六の中心を持つ円柱に内接する四角柱
|
 |
|
|
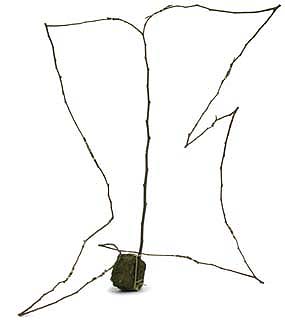 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
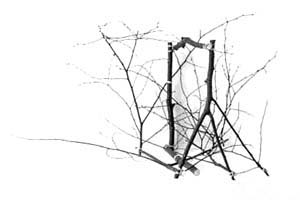 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
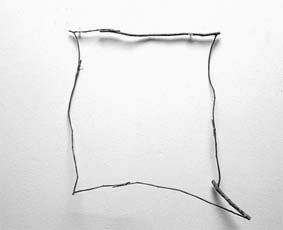 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
それがどうしたと言われても困るし、くだらないと言われれば二の句はない。 |
 |
|
|